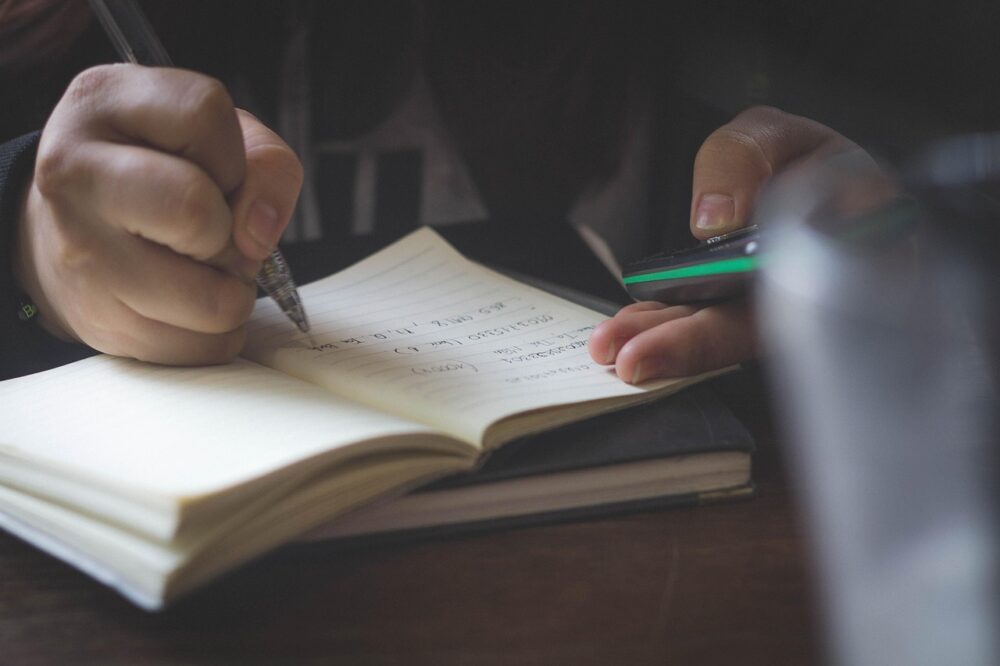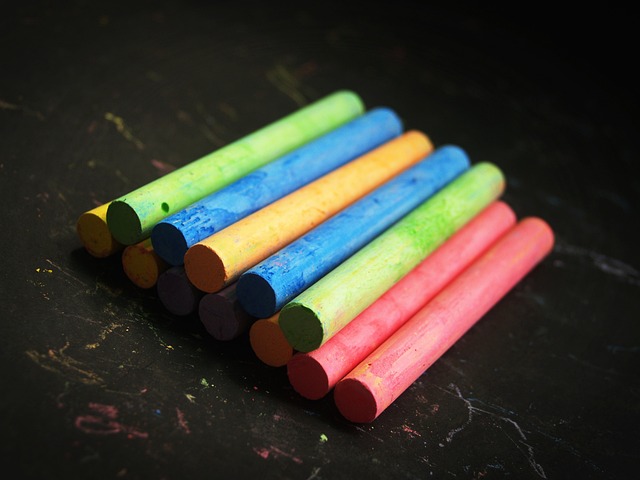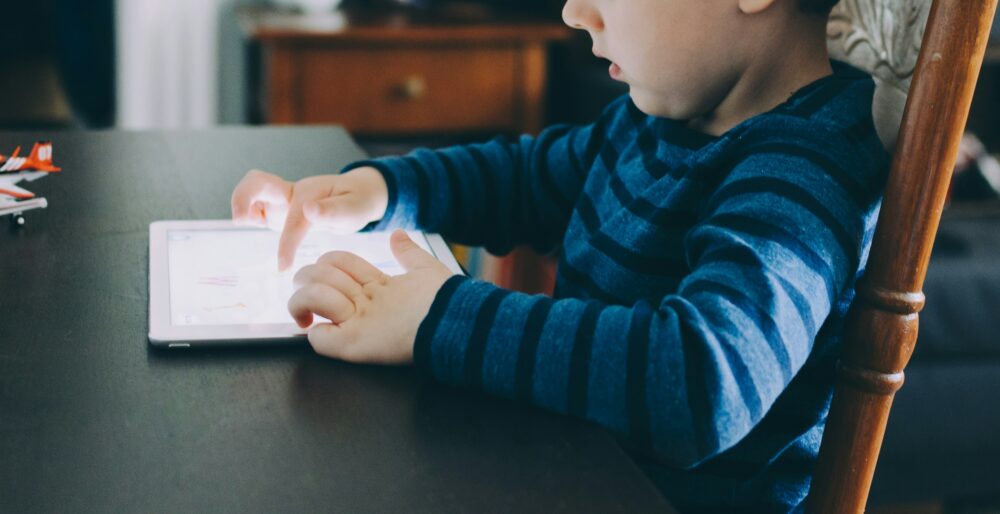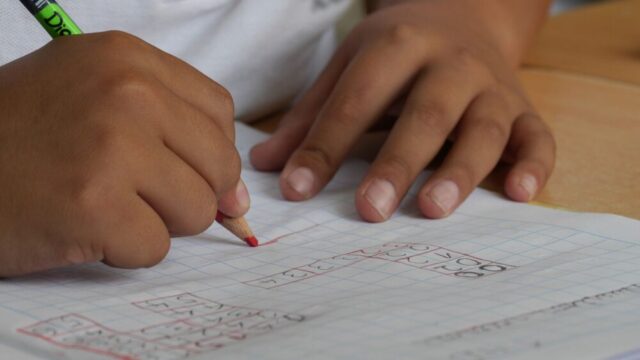- ・授業が難しいみたい…
- ・最近わからないって言ってる…
- ・授業が楽しくなさそう…
そんな悩みを抱える小学生、保護者が年々増えています。
現役の小学校教師として、私は日々「授業についていけない子どもたち」と向き合っていますが、特に小3・小4あたりから、学習に対して急に苦手意識を持つ子が目立ってきます。
ですが、心配はいりません。つまずきには「理由」があり、家庭でもできるサポート方法がちゃんとあります。この記事では、授業についていけなくなる代表的なケースと、その乗り越え方を紹介します。
授業についていけない…小学生に実際によくある3つのケース
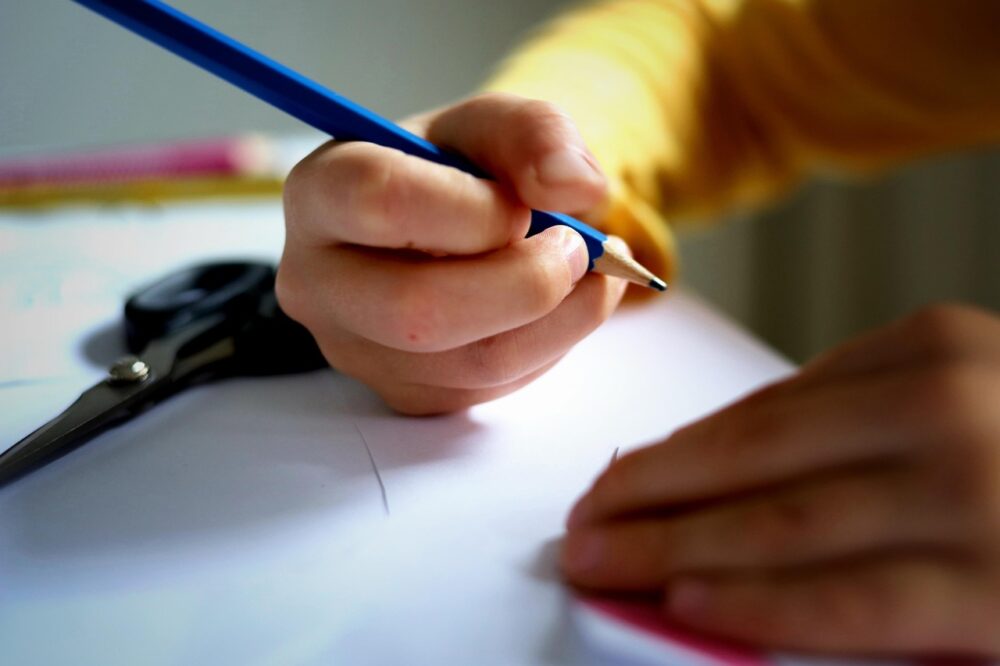
小学生が授業でつまずくのには、いくつかの典型的なパターンがあります。まずは、現場でよく見かける3つの例を見ていきましょう。
抽象思考が求められ、急に理解できなくなる
小学校3〜4年生になると、学習内容が一気に抽象的になります。
「小数」「分数」「図形」「かけ算の筆算」「割合」など、「目に見えない概念」を扱う単元が多くなるからです。
これまで直感的に解けていた子も、理屈やイメージの整理が必要になり、授業についていけなくなりがちです。
こうしたタイミングで「勉強=難しい」と感じると、勉強嫌いになってしまうこともあります。

抽象思考を克服する方法は、やはり「目で見てわかる学び」を用意すること!学校でも、力を入れている先生は多いのではないでしょうか?
スタディサプリのような映像授業は、図やアニメーションを活用して、子どもの理解を助けてくれます。
「つまずき予防」として、動画学習は非常に効果的です。
前の学年内容が身についていないまま次に進んでしまう
小学校の授業は「積み上げ式」です。
「いつから苦手になったのかが分からない」
「何が分からないのかも本人が分かっていない」
「何となく学習へのモチベーションが下がり続けている」
このような状態は、子どもだけでなく保護者にとっても不安の種です。

気付かないうちに、こんな状態に陥ってしまっている子どもや保護者は数えきれないくらい見てきました…
小学校ではできない自分のペースで過去の学年までさかのぼって学び直せるのは映像授業の大きなメリットですよね。
「この単元、抜けてたんだな」「だから、今までわからなかったのか!」と気づけたとき、子どもはグッと成長します。
自信をなくし「勉強=苦手」と思い込んでしまう
このサイクルを繰り返すと、子どもは「自分は勉強ができない」「自分はダメだ」と思い込むようになります。
この自己肯定感の低下が、さらに勉強嫌いを助長します。
保護者が「なんでできないの?」「また間違えたの?」と声をかければかけるほど、子どもは萎縮してしまうのです。
学校生活の大部分をしめる授業時間に「できない」が続くと、自信を無くして当然ですよね。
逆に、「できた!」「分かった!」という小さな成功体験は子どもの自信に直結します。

この小さな「できた」を積み重ねるために、我々教師は奮闘しているわけですが、授業時間だけでは限界も…
そこで強力な相棒になってくれるのが、お家で行う通信教育になります。
スタサプをはじめとした通信教育は、短時間でテンポよく進み、ポイントをしぼって説明してくれるので、理解しやすく、「わかった感」が得やすいのが魅力です。
放っておくと中学校でさらに苦労する
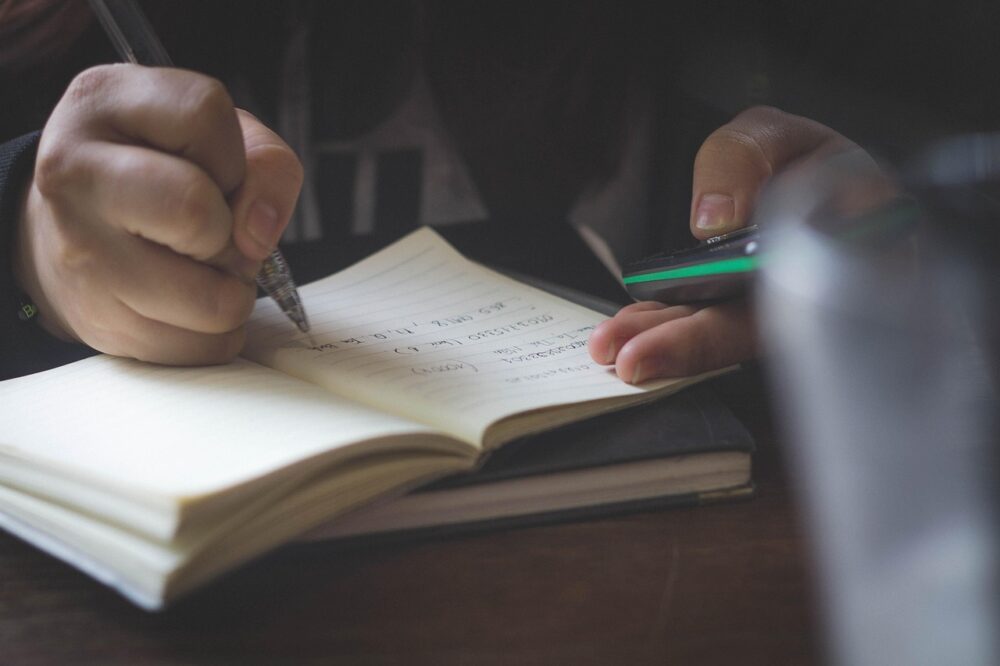
授業についていけない状態をそのままにしてしまうと、中学校に進学した際にさらに大きな壁にぶつかります。
なぜなら、中学校の学習は「小学校内容の理解」が大前提になるからです。
特に数学や英語では、小学校の基礎が理解できていないと、教科書の内容が全く頭に入らなくなります。
実際に中1の1学期でつまずき、自信をなくしてしまう生徒は多いです。

小学校からためてきたつまずきや不安を中学校で爆発させ、犯罪や非行につながったケースも少なくありません。
だからこそ、小学生のうちから「つまずきの芽」を見逃さずに、早めの対策をすることが大切です。
家庭学習の最適解は「スタサプ」
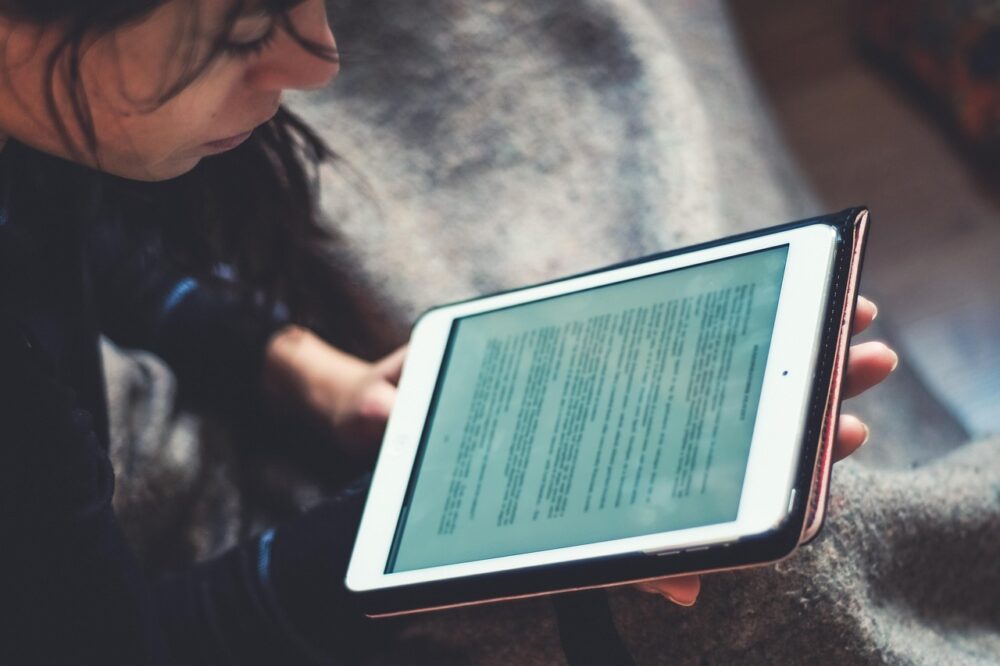
スタディサプリは、私が日々多くの子どもたちと接する中で、「これは間違いなくおすすめできる」と確信している学習サービスです。
その理由を、特に効果が高いと感じる3つのポイントに絞ってご紹介します。
「さかのぼり学習」と「先取り学習」が同時にできる!
家庭学習で大切なのは、子どもの理解度に合わせて「自由に進めること」です。
スタディサプリでは、わからない単元は前の学年にさかのぼって復習でき、得意な単元は先に進める「自由進度学習」が可能です。
たとえば、小4で「分数」が苦手な子が、小3の「小数」や「かけ算・わり算」まで戻って復習することも、得意な子が小5の内容を先取りして学ぶこともできます。
これにより、それぞれの子が「今必要な学び」に集中できるのです。
この「戻れる・進める設計」が、学びを諦めさせず、伸ばす力に変えてくれます。
1回15分の短い授業だから、毎日続けやすい!
スタディサプリの動画授業は、1本あたり約15分と短めに設計されています。
この「ちょうどいい長さ」が、子どもが集中力を保ったまま学べる大きな理由です。
特に家庭では、長時間の勉強は続かないもの。
ですが「とりあえず1本だけやろう」が、自然と毎日の習慣になっていくのです。
この「少しずつの積み重ね」が、最終的に大きな力になるというのが、現場で日々感じていることです。
有名講師による授業で「わかる楽しさ」が実感できる!
子どもが「また見たい!」と思う授業を届けてくれるのが、スタディサプリの講師陣です。
テレビにも出演している有名講師や、指導経験豊富な先生たちが、テンポよく・わかりやすく授業をしてくれます。
「この先生の授業、おもしろい!」と感じたとき、子どもたちの目の輝きが変わるのを私は何度も見てきました。

本当に魅力的な指導をされる講師が多くいます。小学校ではできない指導も満載です
「わからない」が「わかる」に変わる喜び。それこそが、勉強に対する自信とやる気の源です。
忙しい家庭でもスタサプを活用できる3つの工夫

「良さはわかるけど、どうやって通信教育を日々に取り込めばいいのかわからない…」
そんな保護者の声もよく聞きます。でも大丈夫です。ちょっとした工夫で、忙しい共働き家庭でも無理なくスタディサプリを取り入れられます。
1. 学習時間は「毎日同じ時間」に固定する
毎日の生活リズムの中に、学習時間を組み込むことが大切です。
「夜ご飯とお風呂が終わった後の20分」など、無理のない時間帯に固定するだけで、子どもは自然と勉強モードに切り替えやすくなります。
このタイミングなら保護者も横で見守れるので、「わからないところがある?」と声をかけたり、達成を一緒に喜んだりできます。
「決まった時間にやる」だけで、勉強が特別なことではなく「日常」に変わるのです。
逆に、良くないのは「帰宅後、すぐに宿題を終わらせたら遊びに行っていい」というルールです!

この「宿題終われば遊んでいいルール」にすると、「勉強=早く終わらせるべき邪魔者」になってしまうんですよね…
そうして、答えを写す、適当にやる、勉強が面倒くさくなるといった悪循環に陥った子を数多く見てきました。
2. 最初は「1日10分だけ」と伝える
はじめから「30分やろう」「1時間頑張って」はハードルが高すぎます。
「今日は10分だけでいいよ」と伝えることで、子どもが「やってみようかな」と思える心理的なハードルがグッと下がります。
スタディサプリの動画は短くまとまっているため、自然と「もう1本見てみようかな」と、自発的な学習につながりやすいのも特徴です。
「ちょっとだけ」の積み重ねが、やる気と自信を育てていきます。
3. 学習した内容を親子でシェアする
勉強後に「今日どんなことやったの?」と子どもに聞くだけでも、学習効果は大きく高まります。
アウトプットすることで記憶が定着し、「聞いてくれて嬉しい」という気持ちが次のモチベーションにもなります。
保護者が全部見て教える必要はありません。
ただ「関心を持ってくれている」という姿勢を見せることが、子どもにとって最大の応援になります。

私がいつも保護者にオススメするのは、「親も横で勉強する」です!
以下の記事もオススメです!
【まとめ】「わからない」を放置せず、できる学びから始めよう


授業についていけなくなる原因は、単に「苦手だから」ではなく、前の学年の内容が土台として定着していないことにあります。
それを無理に進ませようとすると、ますます苦手意識が強くなり、学びに対する自信を失ってしまうのです。
そんな時こそ、スタディサプリのような「さかのぼり学習」ができる通信教材が力を発揮します。
子どもの理解に応じて、前の単元に戻ったり、逆に得意な内容は先取りしたりできるのが最大の魅力です。
今なら14日間の無料体験も可能。
「うちの子、授業に全然ついていけていない…」と悩む保護者の方は、まずは気軽に体験してみてください。
きっと、子どもに合った学「学び直し」が見つかります。